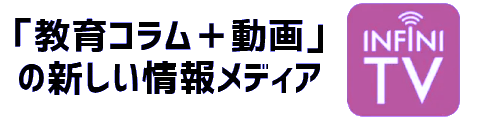246.ワーキングメモリが弱い児童へのサポート①
子どもたちは、自分の困難をうまく言葉にできないことが多く、「自分はダメな子なんだ」と思い込んでしまうことがあります。しかし、先生や関わる大人が少し視点を変えて、「この子は何に困っているのか?」と考えるだけで、その子の学びやすさは大きく変わります。「できない子」と決めつけず「どうすればできるようになるかを一緒に考える」姿勢が、子どもたちの成長を支える鍵になります。
先生や関わる大人に求められるのは、「困っている子どもにいち早く気づくこと」。そして、適切なサポートを行うことで、子どもたちが学びやすく、自信を持てる環境を作ることです。
見過ごされがちな子どもの困りごとの一例として以下が挙げられます。
① 授業中、ボーッとしていることが多い
「やる気がない」と誤解されがちですが、実は先生の話を一度に処理しきれないために、途中で理解が止まってしまっている可能性があります。ワーキングメモリが弱い子 は、先生の説明を最後まで覚えていられず、途中で思考が止まってしまうことがあります。ADHDの子 は、気が散りやすく、授業に集中し続けることが難しい傾向があります。
② 簡単な漢字や計算をよく間違える
「練習不足」と思われがちですが、LD(学習障害)の可能性があるかもしれません。読字障害(ディスレクシア) の場合、同じ漢字を何度も間違えてしまう傾向があります。算数障害(ディスカリキュリア) の場合、数字を逆に読んでしまったり、計算のルールを理解しにくかったりします。
特性がある子どもだけを特別扱いするのではなく、学校等においてはクラス全体が「多様な学び方を認める雰囲気」を作ることが大切だと考えます。
#教育コラム246