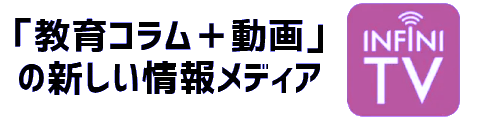244.心豊かな成長を願う
「体験格差」(今井悠介著 講談社現代新書)はセンセーショナルな内容で、著書の「はじめに」では以下のように書かれています。
『私たちが暮らす日本社会には、様々なスポーツや文化的な活動、休日の旅行や楽しいアクティビティなど、子どもの成長に大きな影響を与え得る多種多様な「体験」を、「したいと思えば自由にできる(させてもらえる)子どもたち」と、「したいと思ってもできない(させてもらえない)子どもたち」がいる。そこには明らかに大きな「格差」がある。その格差は、直接的には「生まれ」に、特に親の経済的な状況に関係している。年齢を重ねるにつれ、大人に近づくにつれ、低所得家庭の子どもたちは、してみたいと思ったこと、やってみたいと思ったことを、そのまままっすぐには言えなくなっていく。』
読み進めるにしたがい「したいと思ってもできない(させてもらえない)子どもたち」に胸が締め付けられる思いです。
大人の世界においても、金銭的な豊かさを見せつけるような内容がSNSで拡散されていることから、格差(らしきもの)を私たちは目の当たりにしています。お金の豊かさが全てではないのですが、それでもSNSによる影響力は大きく、大きく自信を失っている大人が後を絶たないようです。
学校での体験活動は子どもたちに公平にその機会があり、また本は図書館で無料で読むことができます。端末にお金はかかりますが、動画はほぼ無料で見ることができる時代になりました。公園の環境整備も進み、野外での遊びも安心できるようになってきました。「したいと思ってもできない(させてもらえない)子どもたち」にとっては、読書や公園での遊びが「したいこと」ではないかもしれませんが、「心豊かな成長を願う」大人が、その素晴らしさを語りかけることも重要な働きかけだと考えます。読書を通して無限の疑似体験ができます。また、「虫捕る子だけが生き残る」とは養老孟司さんの著書にある言葉です。虫捕りを通して得られる体験は尊いものです。「したいこと」ができる日を楽しみに、今できることを楽しむ素晴らしさを私たち大人が声を大にして伝えていきましょう。
<引用・参照>
「体験格差」(今井悠介著 講談社現代新書)
#教育コラム244